

合気道だけやっていても、かなりの運動不足かも
いまやオフィスワーカーの多くがモニター越しの仕事で、目と指しか使っていない時間が圧倒的になっています。暇つぶしもスマホだし、なんだったら脳もそんなに使わない生活になっているのかもしれません。
初めて合気道をする人で、体験に来られる方の中には、今はまったく運動していない。
-
2024年12月30日


当身を含まない理合って成り立つだろうか?
先日、体験に合気柔術をやられている方が来られました。
うちでは他流の方はもちろん、養神館の方でも、所属道場が併修を認めていない限りお断りするようにしています。なぜって、トラブルしかないからです。
体験のページに明記しているのですが、その方は「所属している合気柔術の先生は、併修
-
2024年6月14日

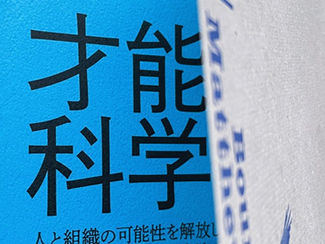
才能は遺伝? それともすべては後天的なのかという問いに
先天的な才能という概念自体が間違いで、ぜんぶ後天的なものだという主張が、異様な説得力をもって迫ってくる本です。
いやいや、そんなことないでしょうよ。
運動能力は千差万別。すぐに出来てしまう人もいれば、なかなか動作を覚えられない人もいる。そう思いながら読んだのですが、なんたって著
-
2022年11月26日


誰でも同じような反応にならないのは、触覚の仕組みなのかも
「人の身体は千差万別。痛めつけないためにも効かせるためにも、相手に最適化した対応が必要」だと考えています。正確には身体そのものではなく、そのときの身体の状態ですが。
稽古が終わってから、「相手の身体がどうかって、どうやって知るんでしょう?」と聞かれました。掛け方ではなくそこか。
-
2022年7月8日


合気道を始めたばかりの人が、とにかく目指した方がいい4つの方向性
合気道初心者が上達するために、いやたぶん楽しんで稽古するためには必要なことですし、何かあったときに、合気道の稽古が役立つためには不可欠なことだと思います。
今回は初心者向けの内容ですので、できるだけカンタンに書いています。
さらに詳しく知りたい方は、リンク先の動画や他の記事に飛
-
2022年2月17日


身体の硬い理由がほとんどメンタルなら、合気道の本質にかかわる問題なのかも
もちろん関節の可動域は人によって様々。運動不足や加齢だけではなく、同じ姿勢でいる時間が長く、使わない筋肉があれば、衰えて硬くなるといいます。 そこを否定するつもりはありませんが、合気道をするのに困るほど可動域が狭いという人に出会ったことがありません。そのことに思い至って、硬いと
-
2021年12月8日


和製英語インナーマッスルの概念を提唱した整形外科医の話は目からウロコだった
肩の筋肉が内側と外側で異なる働きをしていることを解明。この内側の筋肉に「インナーマッスル」と名付け、学会で発表した整形外科医の筒井廣明先生が出演されていました。
私は五十肩ではないので、その治療自体に興味はありません。しかしインナーマッスルを正常に働かせる方法には、もちろん興味が
-
2021年9月30日


膝の作用と壊さない使い方
先日、体験に来てくれた女性に構えを説明していたら、その人の前足の膝がつま先の方向と一致しないので、あわてて「つま先と膝の方向が一致しないと、膝を壊すから絶対にダメです」と説明しました。 けっこうフィットネスをやられている人なのですが、それは聞いたことがないとおっしゃっていました。
-
2021年4月7日


植芝盛平先生は草履で太刀取りされていた
植芝盛平先生は、どうして岩間に野外道場を作られたのか。そしてそこでは素足だったのか、それとも何か履かれていたのか。ということが気になってきて、調べてみました。
コロナ禍の稽古をどうするのか、どんな可能性があるのかを探りたかったのですが、日本だって仮に今より厳しい状況になったとした
-
2021年3月12日


緊急事態宣言を受けての対応について
稽古による感染のリスクは、ゼロではありません。ゼロではないから、リスクは極力減らす。都なら都の規制や要請の内で、できる範囲の稽古による心身へのメリットを最大限にしようと考えます。
今回はもう少しハッキリ書いておこうと思います。
非常事態宣言が解除になって、今まで稽古してきて、多
-
2021年1月9日


『怪我をしない体と心の使い方』は、実質的に使える武道本
それ以上に腕を上げると、肩甲骨が上方回旋します。ポイントを簡単に言うと、肩が上がります。
武道では肩を上げるなと、よく言われます。肩の構造は不安定だからこそ、多様な動きができます。でも肩が上がると、特に持ち上げる動作が不安定になります。
合気道では後ろ技ですね。肘持ちでも両
-
2020年12月31日


痛くならない膝行の方法
私、初心者のころは膝行がキライでした。いや、今でも好きではありませんが(笑)理由はもちろん膝が痛くなるからです。現在では痛くなりませんが、それでも疲れてしまうし、得意ではありません。たぶん稽古量の問題。それほど稽古してこなかったのです。 自分で工夫しはじめたのは、三段審査を受ける
-
2020年9月2日


正しい抵抗の仕方について考えたこと
上級者は、中級者や初心者の技を受けるときに、「こちらの方向に動かせば崩せる」とか理解や上達を助けるように導いてあげるが当たり前だと思います。
そっちに引っぱってあげるというよりも、洗面ボウルに水を溜めていて、水には出口がない。でも栓を外せば、勝手にそちらに流れ出すというようなこと
-
2020年8月15日


『サッカーと感染症』を読んで
『サッカーと感染症 -withコロナ時代のサッカー行動マニュアル』という本を読みました。
サッカーに興味はないのですが、今のところ感染症の専門家が、スポーツ・運動現場の行動指針を書いた本はないと思います。
本じゃなくても、感染症の専門家が、スポーツする現場に関しての発言を探せませ
-
2020年7月18日


ポストコロナの合気道は、正確に突く/打つ稽古から?
えーっと、そうすると合気道はどうなるんでしょうか?
まあ、やるな。やるなら家庭内で、というぐらいかなと推測します。
【最悪を想定して、いまできることを考えると】
一刻も早い終息を祈るばかりですが、どうなるだろうと予想だけしたところで意味がないので、最悪がどうなるか。最悪の状況に
-
2020年5月6日


なにかとマニアックな二ヶ条論
植芝盛平開祖は「合気道は関節のカス取り」だとおっしゃったとか。
というかこの言葉も塩田剛三先生の『合気道修行』に書いてあるのです。どこに書かれている「カス取り」フレーズも、たぶん出典元は『合気道修行』。そして「手首を鍛錬し、血流を良くして新陳代謝を高める」とも書かれています。し
-
2019年10月13日


合気道の稽古で、ワンツーに対応する必要はある? それともない?
「どうして手を握ったりそんなことばっかりしてるんですか?」と言われました。というと?と聞き返すと「こうされたら、どうするんですか」と顔面にパンチを出してきます。本気で殴ろうという感じではないですが、拳もちゃんと作れているし、軌道もちゃんとストレートです。上半身の動きからして、ボク
-
2018年4月18日


『スポーツ中に起こる突発的な事故』講習を受けて理解した中から、熱中症についてを
日産スタジアムにあるスポーツ医科学センターで、『スポーツ中に起こる突発的な事故 〜そのとき指導者に求められることは〜』という講習を受けてきました(といっても3月のことなんですが)。濃く、とても大事な内容でした。
今回は、梅雨やこれからの季節に注意しておくことが必須な「熱中症」につ
-
2017年7月7日



















